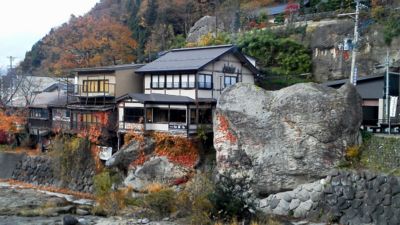|
<<山寺駅>>
山寺に来るのは何度目だろう。でも、車で来るのは、はじめて。
駅が近くにある反面、車が通りぬける道ではなく、なかなか来にくいところにある。
駐車場に車を停める。駐車料金は500円。でも、管理人さんがいない。季節なのに、平日は人を置く余裕がないのだろうか。
結構、駐車場は埋まっている。正直ベースで、料金箱にお金を入れる。
|

|
<<立石川>>
宝珠橋から立石川畔の紅葉を望む。
山寺駅の、正面右側が、展望台になっている。といっても、下からの景色とさして変わるわけではない。
日がさしていて、望遠でばっちりとれるのであれば、いい写真が撮れるかもしれない。
|
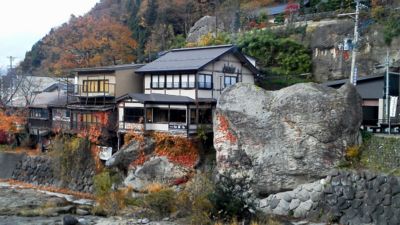
|
<<対面石>>
対岸にある対面石。
宝珠橋からの景色が気持ちいい。川底が石のようで、早い話が、ここら辺一帯が石でできているようなものか。
山寺駅から橋を渡ると、左川に対面石がある。
|

|
<<登山口>>
登山口からすごい石段。今日は、奥ノ院まで行けるだろうか。
時間には余裕があるので、とにかくゆっくりとを心掛け、栄養補給と水分補給も準備万全。
いざ出陣といった気分。
|

|
<<根本中堂>>
何度も来ているのだが、どういうわけか、根本中堂にお参りするのは、これが初めて。
そういえば、いつもは、中抜けして、山門から山登り一本やりのところがあり、ここまで来ることがなかったのだろう。
今日は、端から端までみてやるぞ。
|

|
根本中堂脇の、もみじが色づいていた。バックの暗がりと好対照をなしていた。
黄色いもみじは、これから赤くなるのだろうか。
|

|
<<芭蕉句碑>>
「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」と刻んである。
新しそうであるが、幕末のころの作だそうである。
|

|
<<念仏堂>>
平日のわりに、人出が多い。若いのから年寄りから、カップルからわけのわからない親父まで。
おかげで、気分良く山道を登れそうだ。こんな年寄りが元気に登っているのに、へこたれてなんかいられない、ってね。
|

|
<<山門>>
ここからが有料になる。三門脇の紅葉が大きくて立派。
さあ、がんばるぞ。ゆっくりと、あせらずに、お前にはできるんだ。
|

|
まだまだ、序の口。
ここらは、黄色い葉が多い。日が射すと、とても明るくなる感じ。
|

|
<<空也塔>>
途中には、姥堂、せみ塚、四寸道など、いろいろと見せ場があって、飽きることがない。
これが、一本道の山道なら、すぐ顎が上がってしまうことだろう。
空也塔というのは、あちこちのお寺にあるようだ。山道の途中にも、並んで、建てられていた。
その他にも、観音様なんかの彫り物が、あちこちに祀ってある。
|

|
<<百丈岩>>
見上げるばかりの岩。この上に、納経堂や、開山堂が立っているそうだ。
ここは、直下にあたるようで、上を見ることができない。
|

|
<<弥陀洞>>
岩が阿弥陀様の形に見えるのだそうだ。
4メートルくらいというのだが、それらしきものはあるが、無理やりといった感じなので、多分違うのだろう。
|

|
<<仁王門>>
立派な仁王門。紅葉も立派。ここは、撮影スポットになるに十分な場所だ。YAHOOの投稿写真も、同じ構図のものが多い。
でも、だからこそ、カメラマンの腕が、構図全体の配置に如実に表れるというか、簡単だからこそ、違いが判るというか・・。
撮影スポットとは難しい場所である。
それなりの写真にはなるんですけどね、こんな風に。、
|

|
屋根しか見えないのが金乗院、奥に見えるのが中性院、一番奥の階段を上った先が、奥之院になる。
ここが最後の踏ん張りどころ。十分な休憩をとって、奥之院目指してまっしぐら。
とはいいつつ、よたよたと、最後の石段を登る。
|

|
<<奥之院>>
ここが奥之院。ここまで登るのは、どういうわけか初めて。
いつもは、反対側の、五大堂のほうに先に足が向かってしまって、こっちの方まで気が回らなかったのかもしれない。
石段を登った右側が奥之院(如法堂)、左側が大仏殿。
|

|
<<大仏殿>>
丈六の、金色に輝く、大仏様が、中に鎮座していました。
でも、なんでこんなところに大仏殿を作ったんだろう。
|

|
奥之院からの眺望。
ここまで登って初めてわかる。ここからの眺望が一番だってこと。
五大堂のほうに行きたがるけど、その景色も含めて、ここから見えることになる。
立石川をはさんで、両側に山が迫り、その山が、黄金色に染まっている。
|

|
<<三重小塔>>
奥之院から少し脇に入ったところ。この祠の中に、三重の塔がある。高さは、1メートルくらい。
|

|
記念殿から納経堂を望む。
記念殿とは、明治時代にときの皇太子(のちの大正天皇)の行在所としてたてられたものだそうだ。
たった、一時の滞在のために、建物一つ作るんだからね。
とにかくその建物のところは行き止まりになっているんだけど、そこから、納経堂が眺められる。
立石川向こう岸の山を背景として、納経堂がかっこいい。
|

|
<<胎内堂>>
地図と見比べながら、これは何の建物だろうかと悩んでしまった。
パンフレットの絵地図を見る限り、もっと、下の方にあるはずなんだけどね。
いくつか調べたけど、結局これが胎内堂のようだ。
これは、先ほどの写真と同じ場所から。
|

|
<<納経堂と開山堂>>
奥之院から金乗院のところまで一旦降りて、開山堂方面に向かう。
道は石畳で気持ちいいのだが、端には手すりもなく、ちょっとこわい。
日が陰ってしまったので、写真が色落ちしてしまっている。
|

|
<<五大堂>>
五大堂から山寺駅を望む。
真ん中に、左右に仙山線の線路が通っている。仙台まで1時間、山形までは20分の距離。
おりしも今、山形からの電車が到着寸前である。
左下の橋が、今日の出発点の宝珠橋。その右上、線路沿いに見晴らし台の付いた山寺駅がある。
もう少し右に行った川に面した駐車場に車を止めている。
|

|
五大堂内部。
開山堂の脇を入り、舞台の下をくぐりぬけるようにして五大堂の下を回り込む。
細い石段をあがって、五大堂の内部に入る。
立石川を真下に見下ろして、周囲の山々がきれいに見渡せる。いつまでも見飽きることのない光景である。
|

|
五大堂は、いわつる懸け造りという構造で、代表格は清水寺の舞台ということになる。
山寺には、五大堂をはじめ、先ほどの胎内堂や、釈迦堂も、懸け造りの構造をしている。
ただ、胎内堂も釈迦堂も、見ることはできるが行くことはできない。
行くことができれば、ここと同じか、それ以上の景色を見ることができるのだろう。
ここから先は、修験者のみ立ち入り可能で、下からみて一番目立つ天狗岩の方まで行けるようだ。
|

|
真正面が性相院。
後は下る一方。登りに気を付けたせいか、今日はほとんど疲れなし。こんなに絶好調も珍しい。
私の体力も、まだまだ捨てたものではない。
ルンルン気分で、お家に帰る。
|