2018年9月25日
連休中は、どこも観光客で一杯で身動きも取りにくいし、宿もない。 休みを一日とってゆっくりすることにし、温泉につかって、時間を気にせず明治村を楽しむことにした。
明治村は、全国各地に残っていた明治時代の建築物をここに移築して、公開しているもので、1965年に開村している。
実は40年前、1976年の冬にここを訪れたことがある。その時の写真は横に並べておく。
<<明治村:SLの方向転換>>
|
2018年9月25日 連休中は、どこも観光客で一杯で身動きも取りにくいし、宿もない。 休みを一日とってゆっくりすることにし、温泉につかって、時間を気にせず明治村を楽しむことにした。 明治村は、全国各地に残っていた明治時代の建築物をここに移築して、公開しているもので、1965年に開村している。 実は40年前、1976年の冬にここを訪れたことがある。その時の写真は横に並べておく。 |
|
<<明治村:SLの方向転換>> |
|
|
<<入場口>> あいにくの小雨。けど、傘をささなくても済む程度。 お客さん少ないかな、とは思いつつも、同じ方向に行く車がない。 まさか今日は休園ではと心配になってくる。 駐車場で確認し、開園しているということを聞いて、ほっと一息。 さすがに、券売機も、入口も並ぶ必要がなかった。 <<5丁目付近>>  明治村では、明治が続いている。 今年は、明治151年だ。 <<SL名古屋駅>> 一番遠いところまで行って、徐々に戻ってくるようなルートを考えた。 まずはSLに乗って名古屋駅まで、そこから村営バスで、正門前へ。 |
|
|
<<第八高校正門>> 名古屋市の旧制第八高等学校の正門。 この門は、明治村の正門を兼ねている。 駐車場からは一番遠いのだけど、ここが明治村の正門で、バスとかで来る人はこちらから入村するらしい。 |
|
|
<<聖ヨハネ教会堂>> (重要文化財)京都市の京都五條協会。 正門のところで、ボランティアの案内係のおばさんにつかまり、一緒に案内してもらう。 説明してもらうのはありがたいのだけど、サッサと回りたい心境。複雑。 |
|
|
|
|
|
<<学習院長官舎>> 東京都豊島区の学習院長官舎。 |
|
|
<<西郷従道邸>> (重要文化財)東京都目黒区の西郷従道邸。 案内してもらう人がいないと中に入れない。案内のおばさんとはここでお別れ。 |
 |
<<森鴎外・夏目漱石住宅>> 東京都文京区の森鴎外・夏目漱石住宅。 明治23年から1年ほど森鴎外が居住し、明治36年から3年ほど夏目漱石が居住していた。 他の住宅とは異なり、特に本人たちの好みに合わせて建てられたものではなく、 一般向けの住宅(借家)であるため、実際に、他人の家を覗いているような感覚がする。 前日のサツキとメイの家(昭和の家)に続いて、今日は明治の家をみることになった。 |
|
|
<<レンガ通り>> 展示物は前回の40年前と変わるわけもないのだけど、ここは建造物が増えて、雰囲気が一新している。 <<東山梨郡役所>> (重要文化財)山梨市の山梨郡役所。 明治村の村長は、阿川佐和子さん。ここには、村長室があり、阿川さんがいらっしゃいます(もちろん写真)。 |
|
|
<<札幌電話交換局〜安田銀行会津支店>> 奥から、 (重要文化財)名古屋市の東松家住宅、 京都市の京都中井酒造(ちょっと見えにくい)、 会津若松市の安田銀行会津支店、 (重要文化財)札幌市の札幌電話交換局。 |
|
|
<<京都七条巡査派出所>> 京都市の京都七条巡査派出所。 後方に、元名鉄(名古屋電気鉄道)の市電。 多分、前回来た時には、ここに警官(もちろん偽物)がいて、道案内などをしていたような気がする。 休日のみのサービスかな? |
|
|
<<北里研究所本館・医学館>>
東京都港区の北里研究所本館。 |
|
|
<<幸田露伴住宅「蝸牛庵」>> 東京都墨田区の幸田露伴住宅「蝸牛庵」。 幸田露伴が、明治30年からほぼ10年間暮らした家。 前の、森鴎外・夏目漱石住宅と比べると、中が広々としており、庶民の家とは違う雰囲気があった。 |
 |
一番気に入った場所。 玄関を入った正面に、棚と窓があり、座敷が見通せる。 ちなみに、窓に移っている黒い影は、幽霊などではなく、撮影者(私)である。 |
|
|
<<西園寺公望別邸「坐漁荘」>> (重要文化財) 清水市の西園寺公望別邸「坐漁荘」。 一転、さすがに政府の重鎮の別邸である。隅々まで、好みに合わせて作ってあると見えた。 二階からは、湖(入鹿池)が見通せる、思わず、この景色を西園寺公望も見ていたのかと思ってしまった。 この建物は移築されているので、実際は、太平洋(右に清水港、左に伊豆半島)が見えていたという。 晩年は、車いす生活だったということで、敷居が低く、部屋の床と同じ高さ、今でいうバリアフリーになっていた。 建物に囲まれた中庭の風景。日差しが暖かい。 |
|
|
<<品川燈台>> (重要文化財)東京都港区の品川燈台。 |
|
|
<<宇治山田郵便局舎>> (重要文化財)伊勢市の宇治山田郵便局舎。 ここでは、実際に郵便業務が行われており、郵便を出すことができる。 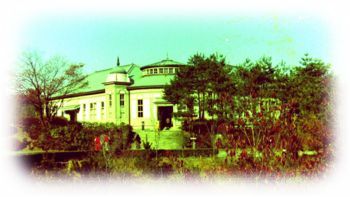 様々な時代の郵便ポストが並んでいる。 |
|
|
<<呉服座(くれはざ)>> (重要文化財)大阪府池田市の呉服座。 昔の芝居小屋と言えば、四国香川の金丸座を思い出す。少しこちらのほうが小振りかな。 でも、造りはほとんど同じ(当たり前かな)、ある程度、それなりに完成した形らしい。 |
|
|
|
|
|
<<本郷喜之床/小泉八雲避暑の家>> 左側が、東京都文京区の本郷喜之床、 右側が、焼津市の小泉八雲避暑の家。 本郷喜之床の二階には、明治42年から2年ほど、石川啄木が家族で暮らしていた。 二階から見えているのが石川啄木(写真)である。 小泉八雲避暑の家は、昔は魚屋だったらしい。今、一階では、駄菓子を売っている。 |
|
|
<<半田東湯>> 愛知県半田市の半田東湯。 店の前には、うどん屋の屋台が。 芝居を見て食べるのか、ふろから上がって食べるのか、どちらでもお腹のすくことだ。 |
|
|
<<聖ザビエル天主堂>> 京都市の聖ザビエル天主堂。  恥ずかしながら、昔と同じ写真を撮っている。 進歩していないなあと思う。 もっというと、次の写真も同じ構図でとっていた。 |
|
|
<<大明寺聖パウロ教会堂>> 長崎県西彼杵郡の大明寺聖パウロ教会堂。 外見は特に特徴のない建物で、他の並びいる建物よりも魅力がないと思うのだが、 ひとたびその内部に入ると、思いもかけない光景が目に入る。まるで、別世界だ。 内部の天井は、大浦天主堂を彷彿とさせるアーチ型をしている。 余計な飾りがない分、こちらのほうがさっぱりとした美しさを感じる。 内部の、右奥に白いものが見えるが、これがマリア像で、いわゆる「ルルドの洞窟」と呼ばれるものである。 フランスのルルドの町の洞窟にマリア様が出現した「ルルドの奇跡」がおきたのが、1858年のこと。 その後、その奇跡にあやかって、洞窟の再現が試みられた。これを「ルルドの洞窟」という。 この教会堂が建てられたのは、1879年のことで、わずか20年前の出来事であった。 |
|
|
<<内閣文庫>> 東京都千代田区の内閣文庫。 何の建物かというと、当時の明治政府の中央図書館である。 |
|
|
<<金沢監獄正門>> 金沢市の金沢監獄正門。 今は門のところだけであるが、当然のことながら、当時はこの両側というか、 敷地全体をレンガの塀で囲んでいたわけである。 |
|
|
<<金沢監獄中央看守所・監房>> 金沢市の金沢監獄正門中央看守所・監房。 中央看守所は八角形の建物で、正面とその左右の面を除く五面に監房舎が設けられている。 ここでは、一カ所のみ監房が再現されており、他は内部にダミーの写真が貼ってある。 中央看守所の屋根の上には、見張り所がある。 中央看守所の真ん中に監視室がある。この監視室は、金沢監獄ではなく、網走監獄のもの。 監視室から、監房の廊下が見通せる。 |
 |
<<帝国ホテル中央玄関>> 東京都千代田区の帝国ホテル中央玄関。 昔からある、明治村のシンボル的な建物。  |
|
|
<<高田小熊写真館>> 新潟県上越市の高田小熊写真館。 二階に写真スタジオがあり、天窓から豊富な明りを取り込める構造になっている。 結局かなり時間オーバーして入口に戻ることができた。 できれば、天気の良い日に、ゆっくり回りたい。 |