2019年9月15日
下北半島は遠くて広い。ほんの何カ所かをめぐるだけなのに、丸一日を費やすことになる。 尻屋崎、恐山、大間、仏が浦。それでも、諦めたところが何カ所もある。 学生の時に来たときは、仏が浦だけしか行くことができなかった(しかも船で)。 今回は、何十年ぶりかの再訪となる。

<<仏が浦>>
|
2019年9月15日 下北半島は遠くて広い。ほんの何カ所かをめぐるだけなのに、丸一日を費やすことになる。 尻屋崎、恐山、大間、仏が浦。それでも、諦めたところが何カ所もある。 学生の時に来たときは、仏が浦だけしか行くことができなかった(しかも船で)。 今回は、何十年ぶりかの再訪となる。 |
 <<仏が浦>> |
   |
<<尻屋埼灯台>> 尻屋崎に建っている記念碑には、本州最北端でも最東端でもなく、「本州最涯地」とある。 まさに、荒れ果てた岬にぴったりの言葉に思われる。 空も、雨こそ落ちてこないものの、厚い雲が広がり、最果ての地にふさわしい空模様になっている。 それでも、時折、雲の隙間からのぞく日の光が、かえって明るさを感じさせる。 下北半島の太平洋岸には、日本で最大規模と言われる猿ヶ森砂丘があるが、大部分は自衛隊の試験場となっており、 一般人の立ち入りはできない。さらにその南は、東北電力東通原発が建設中である。 つまり、ほとんど一般人の立ち入ることのできない地域ということになる。 尻屋崎に行くには、北の海峡沿いの県道6号を利用する。 ここも、昨日の津軽半島沿いの海岸道路と同じく、岩場のきれいな景色が続く。 尻屋崎は、岬の先端部が寒立馬(この地方の在来馬)の放牧場となっている。 馬が逃げ出さないように、ゲートで仕切られており、昼間しか立ち入ることができない。 夏は、朝は7時から夕方4時半まで。ゲートは時間内なら自動で開閉する仕組みになっている。 ゲートをくぐってから灯台までの道路も、気持ちのいいドライブコースである。 尻屋埼灯台、塔高32.8m。 中を見学できる灯台の一つであるが、今日は時間が早くて、中に入ることはできなかった。 ここには、いろいろの逸話が残っている。 曰く、隕石が落ちてきた話。 曰く、戦後被災した灯台が明かりを発していた話。 などなど。 いろいろ調べると興味深いところがある。 |
  |
<<尻屋崎:寒立馬>> なかなか寒立馬に出会うことができなかったが、いざ帰ろうとするとゲートの出口のところで、 待ち構えていたかのように集団で現れた。 寒立馬は、南部馬の系統をひくこの地独特の農用馬で、現在約40頭ほどが、この尻屋崎の地で放牧されている。 マタギたちは、カモシカが、厳寒の中何日も動かずじっと立っている姿を、寒立と呼んでいたという。 寒風吹きすさぶ尻屋崎の雪原にじっと佇む馬の様子から、寒立馬と歌に詠まれたという。 北の最果ての地で草を食む馬たちを見ていると、よくぞ名付けたと言いたくなる。 |
   |
<<恐山:三途の川にかかる太鼓橋>> いったん、むつの市街地まで戻って、改めて恐山に向かう。 恐山とは何なのだろう。名前自体が、恐ろしい雰囲気を醸し出している。 ただ、恐山という山はなく、宇曽利山湖を囲む8峰を総称した名称である。 周辺一帯を含めてこの世のものとは思えない世界を作り上げている。 風変わりな門(霊場恐山と書いてある)を抜けると、三途の川と呼ばれる橋にさしかかる。  橋のたもとに駐車スペースがある。その目で見ると、恐ろしげな色をした川であり、湖である。 お寺の入口には、阿弥陀如来来迎の像が立っている。 何か、如来様という感じのしない、高僧のようなお姿の像である。 |
  |
<<恐山菩提寺:山門>> 立派な山門が待ち構えている。平成元年(1989年)の建立という。 山門の先の地蔵堂、本尊は伽羅陀山地蔵大士。 境内に入ると、一層、異様な雰囲気に包まれる。 硫黄のにおいがあたりに立ち込めている。 恐山は比叡山・高野山と並んで、日本三大霊山に数えられる。 山門前には、風車が数多く立てられ、風に吹かれて回っている。 |
 |
<<恐山菩提寺:本堂>> 山門の脇には、本堂がある。 山門の場所と、ちょっとそぐわない。何かわけでもあるのかな? 祀られているのは釈迦如来。 本堂の隣の建物で、イタコさんの口寄せが行われていた。 数は少ないながらも、順番を待っている方がおられた。 |
 |
<<恐山菩提寺:境内全景>> 正面にあるのが地蔵堂、背後の山は地蔵山。 参道の左右にある建物は共同浴場(温泉)、左側が女湯(2棟)、右側が男湯(1棟)であり、誰でも入ることができる。 女湯の先には地獄めぐりの荒涼とした風景が広がっている。 参道わきの側溝には、硫黄の塊ができている。 背後の山を除くと、立木や草が一切ない。 |
 |
<<恐山:奥の院>> 地蔵堂の脇を廻って山に分け入っていくと、奥の院、というか不動明王像がある。 像の前にあげられているお賽銭の硬貨が、ガスの影響か変色していた。 |
  |
<<恐山:地獄めぐり>> これぞ恐山といった光景。 荒れ地のあちこちから、火山性のガスが噴き出している。 ところどころに、仏像や小さな祠があり、風車が回っている。 |
  |
<<恐山:宇曽利山湖>> 恐山という名前は、宇曽利山(うそりやま)湖からきている。 「うそり」はアイヌ語が語源とされ、入り江や湾を表すという。 宇曽利山湖から流れ出ている川は、先ほどの三途の川(正式名:正津川)のみである。 早いうちから宇曽利山湖の水面が見え隠れしていた。 曇り空ではあるが、この世のものとも思えぬ美しい湖だった。 火山性の物質の影響で、生物が生存できないのだろうか、汚物が一切ない感じがする。 (実際には、ph3.5の強酸性で、魚はウグイのみが生存、水生昆虫やプランクトンなどが確認されているという) 極楽浜は、湖の色に似あう真っ白な浜である。 これだけ見たら、どこかのリゾート地のような感じがする。 恐山8峰のうちの剣山の噴火で形成されたカルデラ湖で、恐山8峰が外輪山をなしている。 湖はハートの形をしていて、窪んでいるところに恐山菩提寺の境内がある。 |
 |
<<大間埼灯台>> ここにきて、初めて連休らしい人混みに遭遇した。 でも、他の場所では、それらしい人混みはなかったので、どこに行っていたのだろう。不思議。 大間埼灯台は、大間崎の沖合にある弁天島に建てられている。 塔高25.4m。 |
 |
<<大間崎:本州最北端の碑>> ここは、本州の最北端。 モニュメントも含めて、尻屋崎や龍飛崎のような荒々しい岩場がなく、海岸まで降りることができる。 |
 |
<<大間崎:マグロのモニュメント>> 大間と言えばマグロ、ということでマグロの一本釣りのモニュメントがある。 付近には、マグロを食べさせてくれる店が立ち並ぶが、どこも満員で大変。 けどやっぱ、本物は高いよね。 |
 |
<<大間崎から函館山>> ここから、北海道が見える。というより函館が見えるといったほうが良い。 目の前の島のように見えるのが函館山だとわかりびっくり。こういう風に見えるのかという新鮮な驚きがある。 さらに、目を凝らすと、市街地のビルや五稜郭タワーの特徴ある姿もなんとなく見える。 たいして良い天気ではないのだが、返って靄らずに形が見えたのかもしれない。 水面が函館の地面より高く見えている。やっぱり地球は丸いんだね。 ちなみに、大間-函館間は約30kmで、大間崎約10mの高さの場合の水平線は12km先。函館は25m海面下に見えるはず(計算上)。 |
  |
<<仏が浦>> 下北半島をマサカリに例えると、まさに刃の部分にあるのが、仏が浦である。 険峻な海岸に、南北2kmにわたって、奇怪な形状の断崖や岩石が連なっている。 緑色凝灰岩でできた岩石が長年にわたって海蝕を受けて刻まれた地形という。 大正11年(1922年)、この地を訪れた文人大町桂月が、 神のわざ 鬼の手つくり仏宇陀 人の世ならぬ処なりけり と詠み、この地を世に広めたという。  =大町桂月の碑= |
 =五百羅漢= |
 =天竜岩= |
 =蓬莱山= |
 =蓮華岩= |
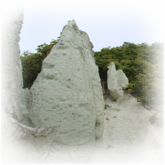 =仁王の顔と双鶏門= |
 =如来の首= |
 =一ッ仏= |
 ※左端が天竜岩(裏側)、右端が蓬莱山と一ッ仏、五百羅漢や仁王の顔は天竜岩の向こうにある。 |