2021年9月17-18日
佐渡は文化的にみると、国仲の公家文化、小木の町人文化、相川の武家文化の三つに分けられる。 はからずも、一日目は国仲平野中心、二日目は南部の宿根木集落、そして、三日目に相川の佐渡金山という日程になった。
台風の余波で、風こそないものの、朝から強い雨が降っている。 でも、今日は山の中の坑道めぐりだから関係ないかなどと、甘いことを考えていた。

<<北沢浮遊選鉱場>>
|
2021年9月17-18日 佐渡は文化的にみると、国仲の公家文化、小木の町人文化、相川の武家文化の三つに分けられる。 はからずも、一日目は国仲平野中心、二日目は南部の宿根木集落、そして、三日目に相川の佐渡金山という日程になった。 台風の余波で、風こそないものの、朝から強い雨が降っている。 でも、今日は山の中の坑道めぐりだから関係ないかなどと、甘いことを考えていた。 |
 <<北沢浮遊選鉱場>> |
  |
<<佐渡奉行所>> 佐渡は佐渡金山があったため、江戸時代は幕府の直轄地で、佐渡奉行所が置かれていた。 当時の資料に基づいて、平成12年(2000年)に、役所の公的部分及び勝場と呼ばれる選鉱工場部分を復元した。 復元して時間が経っているので、白木の部分にかなり色落ちが出てきている。 というか、古色を帯びてきたというべきか。 最近では、函館奉行所や名古屋城本丸御殿のような再現建物を見てきたのだが、 出来立ての真新しいものであった。 時間経過によって、こうなるのだろうか。 |
  |
<<北沢浮遊選鉱場>> 佐渡奉行所の隣接地に、鉱山の近代化に貢献した、金銀の選鉱施設群が廃墟として残っている。 もともとは銅の製造過程で行われていた浮遊選鉱法を金銀の採取に応用して、実用化に成功した施設である。 昭和12年(1937年)の日中戦争開始に伴う増産体制の一環として整備された。 昭和15年(1940年)生産を開始し、東洋一の生産量を誇った。 しかし、昭和27年(1952年)の鉱山縮小に伴って施設は廃止された。 現在残っているのは、選鉱場のコンクリート基礎部分と、発電所、そしてシックナー(濃縮器)跡である、 天空の城ラピュタを思わせる、壮大な遺構である。 現在は、佐渡金山の代名詞のような景色となり、夜間ライトアップされている。(下の写真参照) 夕食後、ホテルのサービスで送迎バスが出ていて、運よく訪れることができた。 |

|

|
 | |

|
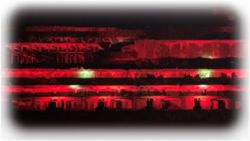
|
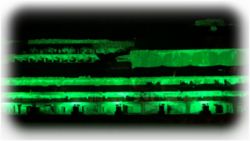 |
  |
<<北沢浮遊選鉱場:50mシックナー>> シックナーとは、大量の液体中に浮遊している固体粒子を、重力の作用により沈殿分離させる沈殿濃縮装置。 泥上の金銀を含んだ鉱石は、この装置で水分を分離濃縮して、対岸の選鉱場に送られた。 ローマのコロッセオを思わせる、壮大な遺構である。 シックナーとは何か分からなくとも、大きな建物は見る者を圧倒する。  |
 |
<<ホテル大佐渡:露天風呂>> 岬の突端にあるホテル、その岬に向かった庭が露天風呂の景色になっている。 開放感たっぷり。変に、塀や岩や生垣で隠されていないのがいい。 |
  |
<<佐渡金山:入口>> 平安時代以前から、佐渡で砂金の形で金が取れたという話はあったが、 本格的に金採掘がはじまったのは、相川で鉱脈が発見された江戸時代以降である。 明治以降は官営鉱山となり、明治後期には民間に払い下げられ、近代的な施設が投入された。 戦時中には、過去最高の採掘量を記録したが、戦後は資源の枯渇もあって規模が縮小され、 平成元年(1989年)に、採掘が中止された。 坑道は総延長が400kmに達するが、その内300mが観光用に公開されている。 観光用の坑道は、二本あるが入口は同じである。ちなみに、出口も同じ場所に出る。 |
 |
<<佐渡金山:宗太夫抗>> 江戸期の手彫りの坑道内に、数十体の人形が配置され、いろいろの作業現場の光景が再現展示されている。 思っていたよりも、精巧な人形で、各場面も平面的でなく立体的に展示されていた。 山奥の坑道を縦横無尽に掘り進んでいく様子が表現されている。 |
 |
 |
 |
 |
<<佐渡金山:道遊抗>> 明治期の坑道。壁はきれいに固められ、地面にはトロッコ用のレールが敷かれている。 ところどころの見所では、照明ががんばっているのだが、派手な割に見せるべきものを見せてくれない。 逆効果だと思う。 個人的に言えば、きれいな写真が撮れない。 |
 |
<<佐渡金山:高任立抗>> 道遊抗の坑道から出ると、高任立抗の櫓が目に入る。 立抗とは、その名の通り、縦方向に掘られた坑道で、地下深くで採掘された鉱石を地上に運び上げるためのものであった。 高任立抗は、明治20年(1887年)に着工され、最深部は地表から659mになるという。 |
 |
<<佐渡金山:高任神社>> 雨が激しくなり、びしょぬれに。カメラを構えている余裕はなく、対象物を収めるのが精一杯。 佐渡金山の一番の見所のところだったのに。 出口から、順路は山の中へ。舗装されている道は、川のようになってきた。 道の先に神社が。鉱山の総鎮守大山祇神社の分社。 佐渡鉱山の初代局長である大島高任の偉業を称えて、この地区を高任地区と呼び、高任神社と呼んだ。 この神社の脇を抜けたところに、道遊の割戸がある。 |
  |
<<佐渡金山:道遊の割戸>> 佐渡金山のイメージの中で最も有名なのが、道遊の割戸のイメージではないか。 高任神社を過ぎて目の前に道遊の割戸があらわれたとき、その荒々しい姿に驚いた。 ここが、道遊の割戸の最下部、この下には先ほど通った道遊抗が通っている。 道遊の割戸は、開山当初から採掘が始まった、最古の鉱区の一つである。 しかも、昭和まで採掘が続けられていたという。 坑道出口まで戻って、逆の道を行くと、おなじみの景色になる。 ただ、雨に煙ってハッキリしないだけでなく、レンズも曇って、うまく撮影できなかった。 |
 |
<<佐渡金山:資料館出口>> 宗太夫抗・道遊抗共に、出口は、資料館になっている。 二階には、佐渡金山の、精巧なジオラマが展示されている。 一階は例によってお土産屋さん。 資料館の出口から100mちょっとで、坑道入口に戻る。 |
  |
<<尖閣湾揚島遊園>> 相川の北にある景勝地。 海岸線を北上し、二つ亀、大野亀と言った名所をたどるつもりであったが、時間の問題で省略することにした。 でも、ここだけは外せない。 雨も少し止んで、傘をささなくてもよいところまで回復してきた。 尖閣湾とは、姫津から北狄に至る約3kmの海岸に広がる、大小5つの湾の総称。 海岸段丘が発達して、30m級の断崖が続く。 また、奇岩・奇勝が連続している。 駐車場から、園内に入ると、たちまち目の前に想像以上の光景が展開する。 橋を渡った岬の先が展望台になっていて、ほぼ360度に近い絶景が眺められる。 |
 |
<<尖閣湾揚島遊園:遊仙橋>> 別名をまちこ橋という。映画「君の名は」のロケが行われた現場である。 岬の先端には、この橋を渡っていく。 |
 |
<<尖閣湾揚島遊園:佐渡大埼灯台>> |
 |
海に向かって滝のような流れが・・。雨のせいかな? |
 |
<<弁慶のはさみ石>> 尖閣湾からは、七浦海岸経由で両津港へ。 距離の問題もあるのだが、昼食の場所にも一苦労しそうだった。 そのため、弾崎経由をあきらめた。 尖閣湾から相川に向かう途中にある。 見ての通りの、アクロバティックな奇岩である。 |
 |
<<七浦海岸めおと岩>> 七浦海岸一番の観光スポット、めおと岩。 ここで、ようやくお昼をいただく。 |
 |
<<本間家能舞台>> 世阿弥の影響で、佐渡には多数の能舞台が現存し、かつ定期的に薪能などの公演が催されている。 本間家能舞台もその一つである。 本間家は、佐渡宝生流家元、灯台で18代を数える。 現在の建物は、明治18年(1885年)の再建で、床下には音響効果用の甕が埋められているという。 雨で、人気もなく、雨戸も締め切って、物寂しい感じ。 |
 |
<<両津港佐渡汽船ターミナル>> 汽車でも、船でも、時間が決まっている乗り物は苦手だ、 道路事情などで、どうしても車での移動には時間の誤差がでる。 そこに、時間が決まっているものが挟まると、どれほど余裕を見たらよいのかがわからない。 遅れてはたまらないので、余裕を見すぎた。 両津港で二時間近く待つ羽目に。 |
 |
<<両津新潟航路>> 当初危惧していたよりも、波が静かで、安心して帰ることができた。 上は、佐渡汽船フェリーときわ丸 下は、佐渡汽船ジェットフォイル |
 |
|