2023年3月21-22日
78番札所からお遍路を再開、残りはわずか。 始まりは、薄曇りだったが、徐々に晴れてきて、日差しが強くなってきた。 遍路の衣装も4年目ともなると、ちょっとよれてきたかな?

<<一宮寺:傘みくじ>>
|
2023年3月21-22日 78番札所からお遍路を再開、残りはわずか。 始まりは、薄曇りだったが、徐々に晴れてきて、日差しが強くなってきた。 遍路の衣装も4年目ともなると、ちょっとよれてきたかな? |
 <<一宮寺:傘みくじ>> |
 |
<<郷照寺(ごうしょうじ):山門>> 四国霊場第78番札所 仏光山郷照寺。 神亀2年(725年)に、僧行基により一尺八寸の阿弥陀如来を本尊とし、道場寺の名で開基された。 醍醐寺開山の理源大師や、浄土宗の基礎を築いた恵心僧都(源信)も、当寺と関りを持つ。 大同2年(807年)には、弘法大師によって伽藍が整備される。 その際に、大師自身の像を彫造して厄除けの誓願を行った。 この像が「厄除うたづ大師」として、現在も信仰されている。 | ||||
 |
<<郷照寺:本堂>> 正応元年(1288年)には、時宗の開祖一遍上人が、遊行の折に3か月逗留し踊り念仏の道場を開いて教えを広めた。 天正の兵火(1576年-1585年)で堂宇を焼失したが、高松藩の庇護により再興する。 これを機に、時宗に属し郷照寺と改称し、真言・時宗の二つの宗派が共存する寺院となった。 本堂は、江戸時代の再建。 | ||||
  |
<<郷照寺:大師堂>> 本堂わきの階段を上った先に大師堂がある。
大師堂の地下には、数多くの観音像を収めた、万体観音洞がある。 | ||||
 |
<<天皇寺(てんのうじ):三輪鳥居>> 四国霊場第79番札所 金華山天皇寺。
| ||||
 |
<<天皇寺:本堂>> 天平年間(729年-749年)、僧行基がこの地を訪れ、金山と名付け、薬師如来を本尊とした金山摩尼珠院を開創した。 後に、弘仁年間(810年-824年)に、弘法大師が、神話の時代から霊泉で名高い「八十場の泉」を訪れた際に、 金山権現を感応し、荒廃していた堂宇を再興して、摩尼珠院妙成就寺とした。 本堂正面には「金剛界説法」、背面には「胎蔵界説法」の扁額がかけられ、両方で参拝できる。 | ||||
 |
| ||||
 |
<<国分寺(こくぶんじ):仁王門>> 四国霊場第80番札所 白牛山国分寺。 

| ||||
 |
<<国分寺:鐘楼>> 天平13年(741年)、聖武天皇が発した国分寺建立の詔により全国に建てられた国分寺の一つで、僧行基によって開創された。。 釣鐘は、創建当時から伝わるもので四国最古のものである。重要文化財。 大蛇が頭にかぶっていたとか、城下に移したら戻してくれと訴えたとかの伝説がある。 | ||||
 |
<<国分寺:本堂>> 創建時の講堂の礎石を利用して、鎌倉時代に再建された。重要文化財。 本尊は、丈六の木造千手観音立像(像高524cm)。平安時代末期の作で秘仏。開帳は60年ごと。重要文化財。 本堂の前には、創建時の金堂の礎石が並んでいる。 現在の唐招提寺金堂に匹敵する規模であったらしい。 境内には、他に七重塔の礎石も残されている。 | ||||
  |
<<国分寺:大師堂>> 中門を抜けたところが参拝殿となっており、そこから隣の大師堂内を拝む形になる。 参拝殿の中には、納経所や売店がある。
大師堂(弘法大師礼拝殿万霊塔:左の写真)には、入れないようになっている。 鉄筋コンクリート造の多宝塔形式で、昭和初期の建立だという。 | ||||
 |
<<国分寺:弁財天>> 本堂前の池には、弁財天の祠があり、周りを七福神が取り囲んでいる。 | ||||
  |
<<白峯寺(しろみねじ):山門(七棟門)>> 四国霊場第81番札所 綾松山白峯寺。
享保9年(1724年)の建立。 重要文化財。 | ||||
 |
<<白峯寺:鐘楼>> 明治時代の再建。 本堂に向かう石段の途中に鐘楼が見える。 石段を通り過ぎたところに、頓証寺殿がある。 | ||||
  |
<<白峯寺:勅額門>> 長寛2年(1164年)、崇徳上皇が流刑先の讃岐で崩御し、当地の稚児嶽上で荼毘に付され陵墓が造られた。 建久2年(1191年)、後鳥羽天皇により、流刑先で過ごした建物を移築して法華堂を建て、頓証寺とした。 応永22年(1415年)、後小松天皇は上皇の成仏を願い自筆の「頓證寺」と書かれた勅額を奉納した。 勅額門は、延宝8年(1680年)建立、重要文化財。 <<白峯寺:頓証寺殿拝殿>> 延宝8年(1680年)建立、重要文化財。 もともとこの建物は、崇徳天皇の廟所として頓証寺という名で建立された。 しかし、明治となって金刀比羅宮の摂社白峯神社となり、その後金刀比羅宮から返還され、頓証寺殿という名になったそうだ。確かに、神社かお寺かわからない、どっちつかずの名前になっている。 頓証寺殿の奥には、崇徳天皇白峯陵がある。 | ||||
 |
<<白峯寺:薬師堂と行者堂>> 石段を登っていくと、左側には、下から薬師堂、行者堂、阿弥陀堂と続く。 薬師堂は、19世紀前期建立。重要文化財。 行者堂は、安永8年(1779年)再建。重要文化財。 境内には、各お堂に、十二支の守り本尊と、七福神を祀っている。 |
 =子= |
 =丑= |
 =寅= |
 =卯= |
 =辰= |
 =巳= |
 =午= |
 =羊= |
 =申= |
 =酉= |
 =戌= |
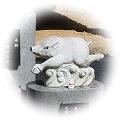 =亥= |
  |
<<白峯寺:本堂>> 99段の階段を昇り詰めると本堂がある。 慶長4年(1599年)の再建。重要文化財。 本尊は、千手観音菩薩。脇侍の、馬頭観音、愛染明王と合わせて秘仏。 弘仁6年(815年)、弘法大師がこの地に訪れ、白峯山頂(標高357m)に如意宝珠を埋め井戸を掘り、衆生済度を祈願した。 貞観2年(860年)、智証大師(円珍)が、山頂に輝く瑞光を見て登頂し、地主神である白髪の老翁の神託を受け、 霊木で千手観世音菩薩を刻んで本尊として、仏堂を創建したと伝えられる。 白峰寺のある五色台は、白・黒・赤・青・黄の五色の峰からなる山である。 白峰はその最も西に位置する。なお、青峰には、次の札所である根香寺がある。 | ||||
 |
<<白峯寺:大師堂>> 大師堂は、本堂のわきにある。 文化八年(1811年)の再建。重要文化財。 | ||||
 |
<<根香寺(ねごろじ):仁王門>> 四国霊場第82番札所 青峰山根香寺。 

| ||||
 |
<<根香寺:牛鬼像>> 仁王門の反対側、駐車場の奥に牛鬼像がある。 根香寺には牛鬼にまつわる伝説がある。 およそ450年前のこと、青峰山には人間を食べる恐ろしい怪獣、牛鬼が棲んでいた。 村人は、弓の名人山田蔵人高清に頼み、退治してもらうことにした。 高清は、根香寺の本尊である千手観音に願をかけ、そのおかげで牛鬼を見つけ出し、退治することができた。 牛鬼の角を根香寺に奉納し、菩提を弔ったという。 | ||||
 |
| ||||
 |
<<根香寺:白猴欅>> 智証大師が寺院創建の折、この樹を伝って下りてきた白い猿が大師を手助けしたという。 樹齢約1600年の大ケヤキであるが、昭和50年(1975年)頃に枯死した。 その後、平成3年(1991年)に、保存のため、根を切り屋根をつけて、元の場所に現在地に据えている。 | ||||
  |
<<根香寺:本堂>> 弘仁年間(810年-824年)、当地を訪れた弘法大師は、五色台に金剛界の五智如来を感得して、青峰に「花蔵院」を建立した。 天長9年(832年)、智証大師(円珍)は、山の鎮守である一之瀬明神に出会い、蓮華谷の霊木で千手観音像を彫像し、 「千手院」を建てて安置した。 その霊木は香木だったようで、二つの寺を合わせて根香寺と称するようになったという。 本尊は、木造千手観音立像。 平安時代の作で秘仏。重要文化財。 | ||||
 |
<<根香寺:五大堂>> 中央の不動明王は、弘安9年(1286年)に元寇調伏祈願のために作られた。 他の4体の明王(大威徳・金剛・降三世・軍荼利)は、天和3年(1683年)に高松藩主が京の仏師に作らせたという。 
| ||||
 |
<<一宮寺(いちのみやじ):仁王門>> 四国霊場第83番札所 神毫山一宮寺。 

| ||||
   |
<<一宮寺:本堂>> 立派なクスノキに守られるように本堂が建っている。 大宝年間(701年-703年)に、法相宗の祖 義淵により創建され、当初は大宝院と称していた。 和銅年間(708年-715年)に、諸国に一宮が建立された時、讃岐一宮として田村神社が建立され、別当寺となった。 そして、行基が堂塔を修復し、一宮寺に改めたとされる。 大同年間(806年-810年)、弘法大師が伽藍を整備し、聖観音菩薩像を刻んで本尊として安置し、真言宗に改宗した。 <<一宮寺:大師堂>>
<<一宮寺:手水舎>> 屋根の草の生え具合に、趣のある手水舎。 吐水口には、普通は竜が置かれ、吐水竜などと言われるが、ここは大師像が置かれ、その手から水が流れ出ている。 | ||||
 |
<<一宮寺:薬師如来の祠>>
|